医療機関での窓口負担額を抑えたいとき(限度額適用認定証)
限度額適用認定証
自己負担限度額はこちらをご覧ください。
70歳未満の方及び70歳以上で現役並みの所得の方の医療費が高額になりそうな場合、医療機関等の窓口でマイナ保険証等と一緒に「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月の窓口での支払いを一定の金額(自己負担限度額)まで抑えられます。
この限度額適用認定証は、入院時だけでなく外来及び調剤薬局でも使用できます。
入院などで医療費が高額になることが予想される場合に、あらかじめ共済組合に申請して限度額適用認定証の発行を受けておくと、窓口負担が少なくなります。
◎マイナ保険証を利用すると、限度額認定証の事前申請が不要になります。
限度額認定証がなくても限度額を超える支払いの免除がうけられるため、事前に限度額認定証の交付をうける必要がなくなります。
※ 適用区分「オ」・「低所得Ⅰ」・「低所得Ⅱ」の認定を受ける場合は、事前申請が必要です。
限度額適用認定証の申請について
<提出先>
共済サポートデスク(℡078-322-5775)
電子申請が可能です。お急ぎの場合は共済組合の窓口で交付しますので、共済サポートデスクまでご相談ください。(マイナンバーカード等、本人確認のできるものを窓口へご持参ください。)
(※)適用区分「オ」・「低所得Ⅰ」・「低所得Ⅱ」の認定を申請する場合は、組合員または世帯全員の「市区町村民税非課税証明書」を添付してください。
| 様式 | 名称 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 様式3-15 | 限度額適用認定申請書 | (※) |
| 電子申請のみ | こちらから必要事項を入力してください。 ※インターネット用PCからアクセスしてください。 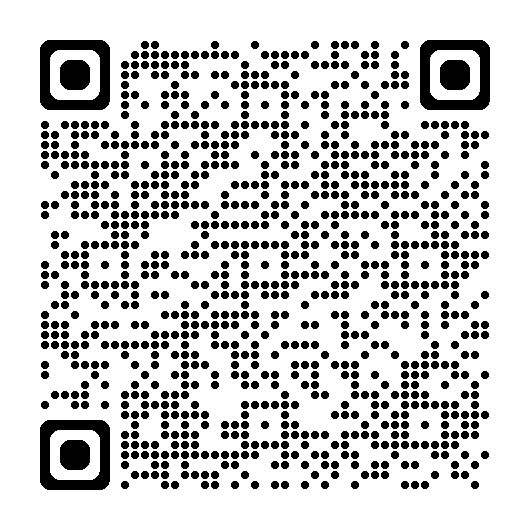 スマートフォンからも申請できます | (※) |
◇ 使用にあたっての注意事項
- 市区町村の制度により医療費助成を受けている場合、「限度額適用認定証」を使用しても医療機関等での窓口負担額はかわりません。
- 申請した日の属する月の初日から有効な「限度額適用認定証」を作成します。
- 資格取得月や有効期限の翌月は、標準報酬月額の決定後に交付します(おおよそ発行月の中旬以降)。
- 有効期限以降も限度額適用認定証が必要な場合や、組合員の記号・番号が変更になった場合は、再度申請が必要です。
- 柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術には使用できません。
- 窓口で支払う自己負担限度額は標準報酬月額に応じて異なります。(標準報酬月額はこちらをご覧ください)
- 自己負担限度額は、ひと月ごと・ひとつの医療機関(外来・入院別 、医科・歯科別 )の支払いごとに適用され、世帯合算や多数該当は考慮されません。それぞれの支払い時に、自己負担限度額までを支払っていただくことになります。
- 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ以外の70歳以上の方については、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので申請は不要です。